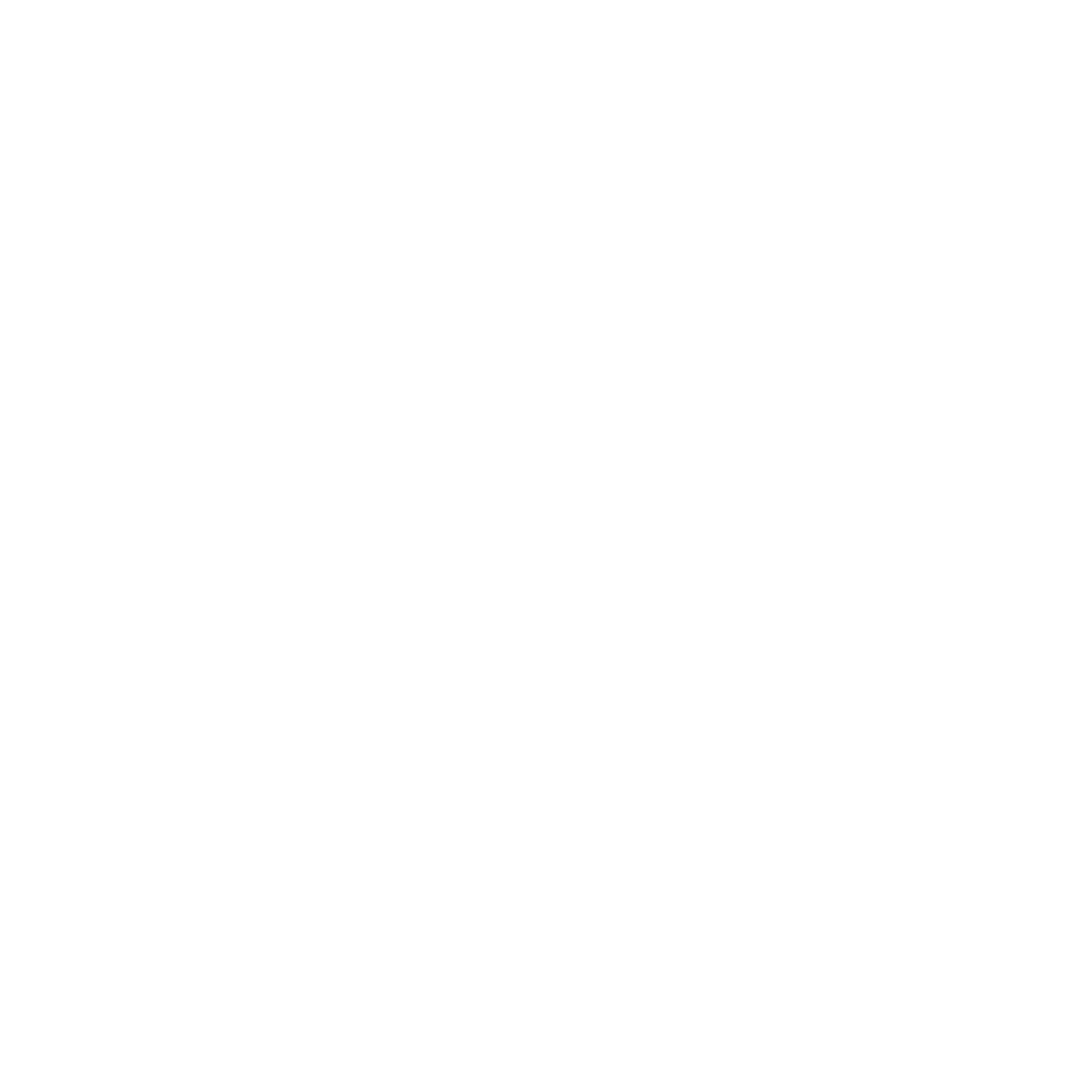皆さん、こんにちは。丘紫真璃です。
今回は、べてるシリーズ第3弾をお送りしたいと思います。
これまで2回に渡って、べてるの家とヨガのつながりをご紹介してきましたので、ぜひ前2回のコラムからお読み下さい。
精神障害を患った人々が集まるべてるの家。全国でも異色の活動として注目を浴びたべてるの家の設立者は、当時の浦賀赤十字病院の精神科でソーシャルワーカーを務めていた向谷地生良さんです。
今回は、この向谷地さんの持つ苦労の哲学を通して、べてるの理念の真髄に迫っていきたいと思います。
べてるの家の設立者

向谷地さんが浦賀赤十字病院のソーシャルワーカーとして勤めだしたのは22歳の時。
そして向谷地さんが牧師のいなくなって無人化していた古い教会堂に住み着いたのは、赴任して2年ほどたった時のことでした。
そこで彼は、精神科を退院してきた佐々木さんという人に出会います。
佐々木さんは一応退院したものの、仕事も頼るべき身寄りもなく困り果てていました。
退院したといっても薬は飲み続けないといけないし、いきなりシャキシャキ働けるわけでもなく、どうすればいいのかすっかり困り果てていた佐々木さんに、向谷地さんがお化け屋敷のようなところでも良ければ来ませんかと声をかけたのでした。
そうして向谷地さんと佐々木さんではじまった共同生活に、1人、2人と仲間が増えていき、「べてるの家」と名付けられます。
それがべてるの家のはじまりでした。
そんな向谷地さんはべてるの人びとと深く関わり、べてるになくてはならない存在になっています。
そして、べてるの家の基本理念である苦労を取り戻す生き方…精神病の当事者が、保護者や家族、医療関係者に保護され代弁されることなく、自らの病気がもたらす苦労や悩みを、自分自身で引き受けるという生き方の根幹には、向井地さんの持つ苦労の哲学があったのです。
その苦労の哲学について、くわしく見ていきたいと思います。
苦労で世界とつながる

1955年生まれの向谷地さんは、苦労の多い学生時代を送ってきました。
子ども離れした落ち着きを備えていたせいか、中学時代には生意気だからという理由で何度も殴りつけられ、一時的に記憶を失うまでの大怪我まで負わされてしまいます。
その後遺症で、1学期まるまる休むことになったというのですから、かなりの大怪我ですよね。
高校と大学時代は勉強そっちのけで、難病団体や障害者団体、難病患者支援活動などに情熱をそそぐようになります。
そうして困難な中で生きる人々の中に身を投じて様々な苦労を重ねながら、向谷地さんはこんな風に感じていたと語っています。
自分が逆境に陥れば陥るほど、なんかこう社会的に知っているベトナム戦争のなかで生きてる子どもだとか、そういうものにまた自分がリンクしていく、同一化していくっていう、そういう感覚ってあったと思うんですね。わたしが自分の弱みっていうんじゃなくて、人として自分は苦労に直面している、この苦労は地球の裏側にある苦労とどっかリンクしているっていう、そういうものがあったんですよね。
(『治りませんように』)
自分の苦労は、他者と、そしてまた地球の裏側の苦労ともつながっているという向谷地さんの考え方に、私は深く感銘を受けました。苦労の哲学の根幹を形作るこの考え方は、ヨガと深く共鳴するのではないでしょうか。
苦労が世界を見つめるまなざしを深くする

『ヨガ・スートラ』をめくると、苦しみを引き受けることによって心は浄化されていくと書いてあります。
人生に苦労はつきものです。どんな形であれ、苦労していない人間など1人もいないでしょう。
そうして苦労をし、悩み、乗り越えて成長していくことで、心は澄んだものになっていくのだとパタンジャリは言うのです。
それはどういうことかと考えた時、他の人の苦労や悲しみに鋭敏になるということなのか
なと、私はそう思います。
例えば、子育てで苦労をするようになると、自分のお母さんは自分を育ててくれた時、こんな苦労をしていたんだなあと、しみじみ感じたりしますよね。
ウクライナの戦時下の中で子育てをしている若いお母さんの苦労を見て涙したりするのは、自分自身が今、日本で、子育ての苦労を重ねているからこそではないでしょうか。
あるいは、仕事の人間関係で苦労をするようになると、やはり、人間関係で苦労をしている別の人の気持ちがよくわかるようになりますよね。
人間関係に悩むあまりに病気になってしまう人や、学校に行けなくなった人など、様々な人の気持ちにより深く寄り添えるようになります。
そういうことが、向谷地さんのいう、苦労で世界とつながるということではないでしょうか。
作者は次のように書き綴っています。
苦労をそのように捉えるとき、私たちもまた自らを開くことができるのではないかと。他者につながることができるのではないかと。そのような苦労を自ら担うことによって、私たちは人間の広い世界と、歴史につながることができる。苦労の哲学はそういっているかのようだ。
(『治りませんように』)
苦労を通して、世界と、そして歴史とつながっていく。
そうした苦労の哲学をかみしめた時、「治りませんように」の本当の意味が、ここで改めてわかってきたような気がしました。
治りませんように

『治りませんように』という題名は、何度見ても衝撃的です。
最初はいったいどういうことなのか、全くわかりませんでしたが、読み進めていくうちに、その本当の意味がだんだんと見えてくるようになりました。
そして、この苦労の哲学まで読んだ時、やっと、私にも、その言葉の意味が腑に落ちてきたのです。
苦労はしなくてすめばしない方がいいなんて単純なものではなかったのです。
苦労するということはそれ自体に意味があったのです。
だから、治りませんようにという言葉の中には、病で起こる様々な問題や苦労を自分自身が引き受けて、自分自身の生を生きたいという思いが込められているのではないかと、私はそう思いました。
医療関係者や家族が、治療によって薬や注射でその症状を抑えてしまうのではなく、病という煩わしさを当事者自らが引き受け、人間としての苦労を重ねること。
そうすることで、他の人と、世界と、歴史と、つながっていきたいという思いがこの「治りませんように」という言葉の中に込められているのではないでしょうか。
べてるの家には、人間とは苦労するものであり、苦悩する存在なのだという世界観が貫かれている。苦労を取りもどし、悩む力を身につけようとする生き方は、しあわせになることはあってもそれをめざす生き方にはならない。苦労し、悩むことで私たちはこの世界とつながることができる。このように生きて死ぬということが、ほんとうに生きるということではないだろうか。そして語りつがれる生き方となり、死に方となるのではないだろうか。その思いが、浦賀の地から、べてるの家から、たえまなく私たちに伝えられている。けっして明されることのないことばとして、だれにも見えない荷物として、私たちに語られ、渡され、そしてまた私たちを通りこして、私たちにつながる他者へと語りかけられ、伝えられてゆく。
(『治りませんように』)
べてるの家から伝わった苦労の哲学は、『治りませんように』という本を通して、私に伝えられてきました。
それが、このコラムを通して、皆さんに少しでも伝わったらとても嬉しく思います。
斉藤道雄『治りませんように べてるの家のいま』みすず書房(2010年)