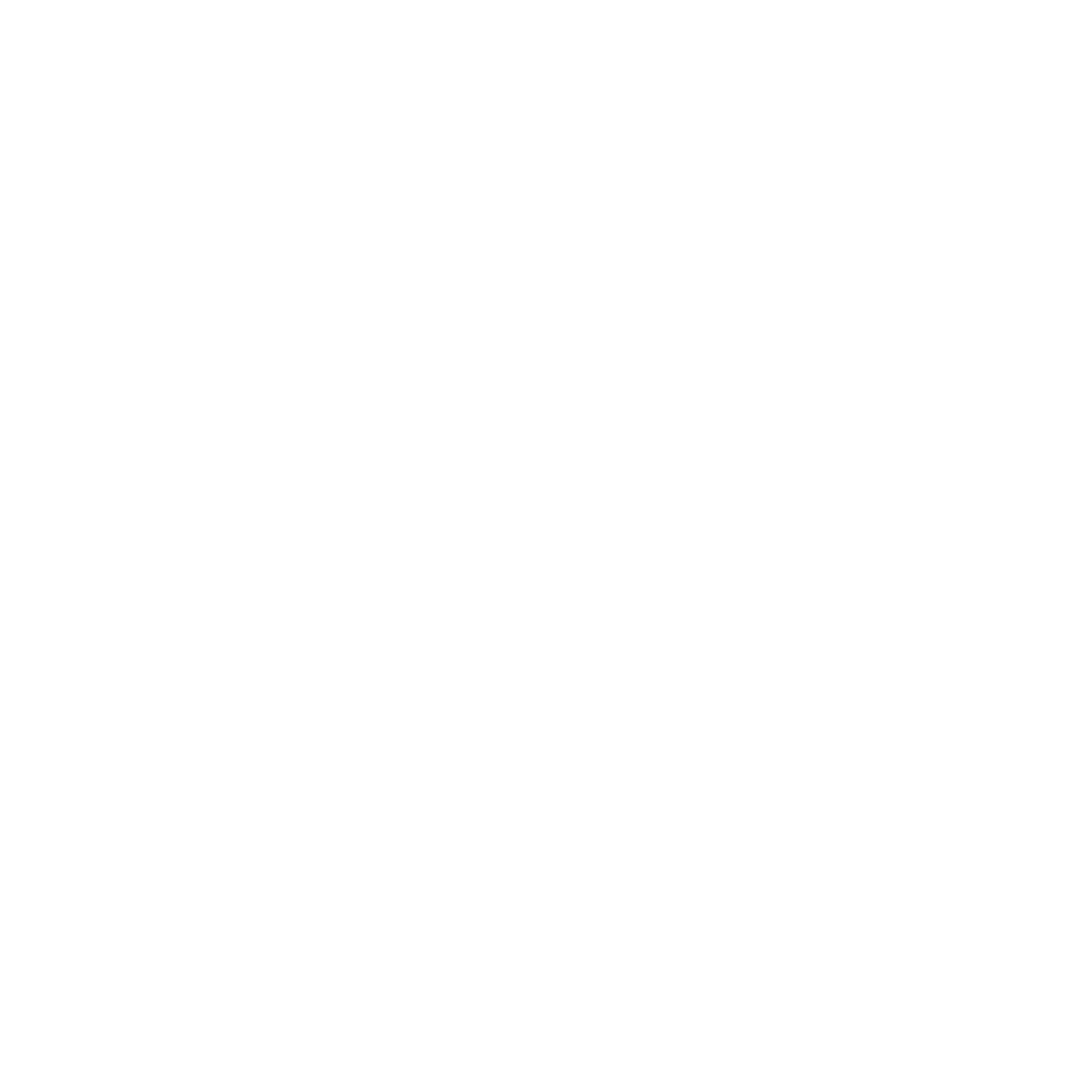こんにちは!丘紫真璃です。今回は、風野潮さんのデビュー作「ビート・キッズ」を取り上げてみたいと思います。
講談社児童文学新人賞、椋鳩十児童文学賞、野間児童文芸新人賞など、数多くの賞を受賞している作品で、大阪の中学二年生の少年が、歯切れのよい関西弁で物語を語っていきます。
胸が熱くなるブラバン物語で、展開がわかっているのに何度でも感動できる名作中の名作。文字で読んでいるだけなのに、ブラスバンドの音楽が耳にはじけるように鮮やかに聞こえてきます。
今回は、そんな大阪の熱いブラバン物語の世界に飛びこんでいきたいと思います!
ページを止めることができない名作「ビート・キッズ」
「ビート・キッズ」は、1998年7月に発表された作品で、今も児童文学作家として大活躍中の風野潮さんのデビュー作となります。この作品が数多くの賞を受賞していることは先ほども書いた通りですが、2005年には映画化もされ、今もなお人気が高い名作です。
歯切れのよい関西弁の語り口で語られていく物語は、次々に怒涛の展開が待っており、一度ページをめくってしまったらもう止めることができません!
バスドラムとの出会い

主人公は、大阪に住む中学2年生、横山英二。物語は、クラスメイトの女の子からブラスバンド部に入らないかと、英二が誘われるところから幕を開けます。
英二を誘ったのは、最近、パーカッションの1年生が退部してしまったため。パーカッションが1人足りないと、来年の万博公園のドリルフェスティバルに出場できなくなるのです。
英二にパーカッションをさせたら良いのではないかと考えたのは、ブラスバンド部の部長、菅野七生。ブラスバンド部の顧問の先生は音楽に関しては素人のため、演奏の指導は、楽器店の息子で、ほぼ全ての楽器に通じている七生に一任されています。
そんな七生は、音楽室に来た英二に、お前にはリズム感があると言いきります。そして、英二をバスドラム(大太鼓)の前に連れていき「たたいてみろ」と、太鼓のバチを渡します。
英二ははじめ、力任せにたたくだけでしたが、叩き方を変えてみると、不思議な楽しい感覚に包まれました。
バチを握った右手を勢いよく上げて、全身跳ねるような感じで、軽く楽しく、手のひらの真ん中を一瞬打って、すぐにまた腕を振りあげた。すると、気持ちいいくらいのわずかな痛みだけを残して、バチは手のひらをパシンとはじいていった。
俺はすぐにそのまま、振りあげたバチを大太鼓の皮に向かって振りおろした。腕もひじも体のほかの部分も、みんな祭りのリズムにのるように軽く楽しく。太鼓の革に一瞬だけあいさつして、すぐもどってくる感じで。
ドォーン! はじけるかと思うほどの大きな音は同じやけど、こんどは部屋の空気全体にそれが、ほわぁーんとやわらかく伝わっていった。腕のしびれも空気の余韻も、こんどはシャーンシャーンというような気持ちいい響きがした。
これは……これは、おもしろいぞ!
(「ビート・キッズ」)
太鼓を叩く感覚に面白さにやみつきになってしまった英二はブラスバンド部のパーカッションを務めることになり、七生や他のブラスバンド部の仲間達と共に、万博公園のドリルフェスティバルを目指して、猛特訓を始めるようになるのです。
ドラムは花火
英二が今まで、部活に入っていなかった理由。それは、家庭の事情によるものでした。英二の父は、お酒や賭け事のせいで、すぐに仕事がクビになってしまうため、仕事を転々としてきました。そのため、英二の家は、かなり貧乏な生活をしています。
英二の母は、優しくて美人で賢いのですが、身体が弱く、無理ができません。しかも今は、妊娠中のため安静にしていなくてはならず、夕飯作りなどの家事は英二が引き受けています。
英二は、最近話題の「ヤングケアラ―※1」なので、部活をしていなかったのですね。
母親に遠慮せずに部活をするようにと言われたこともあってはじめたブラスバンド部ですが、ある日英二は、身体の弱い母親が内職をしているのを見つけます。理由は、父親が賭け事ですってしまい、生活費が足りなくなったからでした。
母親に無理はさせられないと、英二は自分が新聞配達のアルバイトをする決意をします。毎日、新聞配達をするとなると、部活には出席できなくなるため、英二はブラスバンド部をやめる決意をして、部長の七生に話します。
しかし、七生は、部活をやめなくてもできるアルバイトを紹介すると言い、自分の父親の楽器店に、英二を連れていきました。そして、そこの店番を英二に任せたのです。
英二は、七生の楽器店で、はじめてドラムセットというものを目にして息をのみます。
俺はその…ドラムセットを、声もなく見つめた。そのときは、『ドラムセット』というちゃんとした呼び名さえ知らなかった。けれど、本当に、こいつと俺と、ここでこうやって出会うのは運命だったんだとさえ思うほど、強い気持ちで結ばれている気がしていた。
(「ビート・キッズ」)
さらに七生がドラムを叩いてみせてくれ、英二はその音に衝撃を受けて叫びます。
「ドラムは花火なんや! はじけて、光って、響いて、ゆれてる、花火なんや! そやから、俺、花火になりたいねん!」
俺は大マジメに、ドラマーじゃなくて花火そのものなりたいと、思っていた。
(「ビート・キッズ」)
- ※1 ヤングケアラー:一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされる。
花火はサマディー
その後英二は、万博ドリルフェスティバルを目指して、仲間と共に厳しい特訓を続けます。そして本番。ブラバン仲間と素晴らしいマーチングドリルを披露で来た時、英二は再び、鮮やかな花火を目にします。
目の中いっぱいに広がってく、花火の光。全身を包み込んで響く、花火の音。ほんまの目の前には実際のドリルの光景を見ながら、心の中には華やかな花火大会の光景が見えていた。俺の中でふたつの景色がごっちゃになって、まるでドリルの景色の中に花火が散ったり、空気が七色にかがやいたりしているように見える。
(「ビート・キッズ」)
これを読むと、英二はまるでヨギーが瞑想をし、そしてサマディ―を見るように、ドラムを叩き、花火を見るのではないかと思えます。
しかし、万博ドリルフェスティバルが終わった後、英二の家庭状況が暗転し、英二は花火を見るどころか、ブラスバンド部の活動さえ出席できなくなってしまいました。
さらに、親友の七生もプロバンドにスカウトされて東京に行くことになったため、部活に出席さえできない英二は、ブラバンの仲間も、七生も、自分を置いて遠くに行ってしまったような気がして、ますます孤独に追い詰められます。
七生は、英二が好きそうな音楽や、自分のドラム演奏をたくさん入れた MD を英二に届けてくれるのですが、それを聞いても、身も心もボロボロに疲れ切った英二の心には届きません。
どんな音楽を聴いても、もう英二の目には、あの時見えた花火が全く見えないのです。
「上手やなあ。ほんまにええ音で、するどい音で、心臓に響いてくるビートで。こんなに大好きな七生のドラムやのに……。あの日、見えてた花火が、今は見えへん。
俺にはもう、花火が見えへん」
(「ビート・キッズ」)
英二のヤングケアラーぶりはページをめくるごとに激化していきます。それが具体的にどんな状況かということは本でお読みいただくとして、とにかく、英二は死んでもかまわないとさえ思いつめるほどになってしまいます。
けれども、そんな英二を心配して、七生が東京から帰ってきてくれました。
英二は、夜、もうシャッターがおりていた七生の楽器店の中で、七生に胸のうちを全て、ぶつけまくります。七生は英二の叫びを黙って受け止めてくれました。
七生に胸の内をぶつけて、やっと少し心を落ち着けた英二は、七生からドラムスティックを渡されます。七生は、英二にドラムを叩いてみろと言うのです。
初めて目にした時から、ずっとあこがれて、ずっと座りたいと願っていたドラムセットの前に、英二は息を殺して座ります。そして、ゆっくりとドラムを叩きだした途端、心の中に
パァーッと、花火の景色が広がっていったのです。
「なんでこんな、はっきり見えてるんやろ。もう一生見られへんかと思たのに、今、俺の頭の先から足の先まで全部、花火でいっぱいになってる。今まででいちばん、きれいな花火で。
手も足も体も、もう凍えてない。心も、もうふるえてない。(略)
こんなに心のビードがはっきり鼓動を打って、俺を動かしているんやから。俺は、死なへん」
(「ビート・キッズ」)
身も心もボロボロになっていた時、英二がいくら、七生のドラムを聞いても花火を見ることができなかったのは、心があまりにも荒れすぎていたからでしょう。
心が荒れている時、人はうまく瞑想ができません。だから、ヨガをすることで、心を落ち着けようとパタンジャリは言うのです。
英二は、七生に話を聞いてもらうことで、心をどうにか落ち着けました。だから、英二はその後、ドラムを叩いて、再び花火を見ることができたのでしょう。苦しんだ果てに見た花火だったからこそ、英二の心にますます鮮やかに、ますます美しく、ますます力強く迫ってきたのです。
深い瞑想は、生きる力になってくれます。心や体に新たな希望をくれ、もっと前向きに生きようというパワーになってくれます。
「ビート・キッズ」を読む時、私達は、英二と共に泣いたり笑ったり、苦しんだり怒ったりし、英二や七生のドラムから、息がとまるほど鮮やかな花火が打ちあがるのを見ることができます。
若い2人のドラムから打ちあがる力強い花火は、パワーがいっぱいみなぎっていて、疲れ切った私達に力を分けてくれるような……そんな気が、私はします。
だから、疲れたら何度でも「ビート・キッズ」を開き、花火を見に行きたくなります。
コロナ禍で疲れがちな方が多いと思いますが、そんな今だからこそ、「ビート・キッズ」を開いて、花火を見ていただけたらと思います。
参考資料
- 『ビート・キッズ』(2010年:風野潮 著/講談社青い鳥文庫)